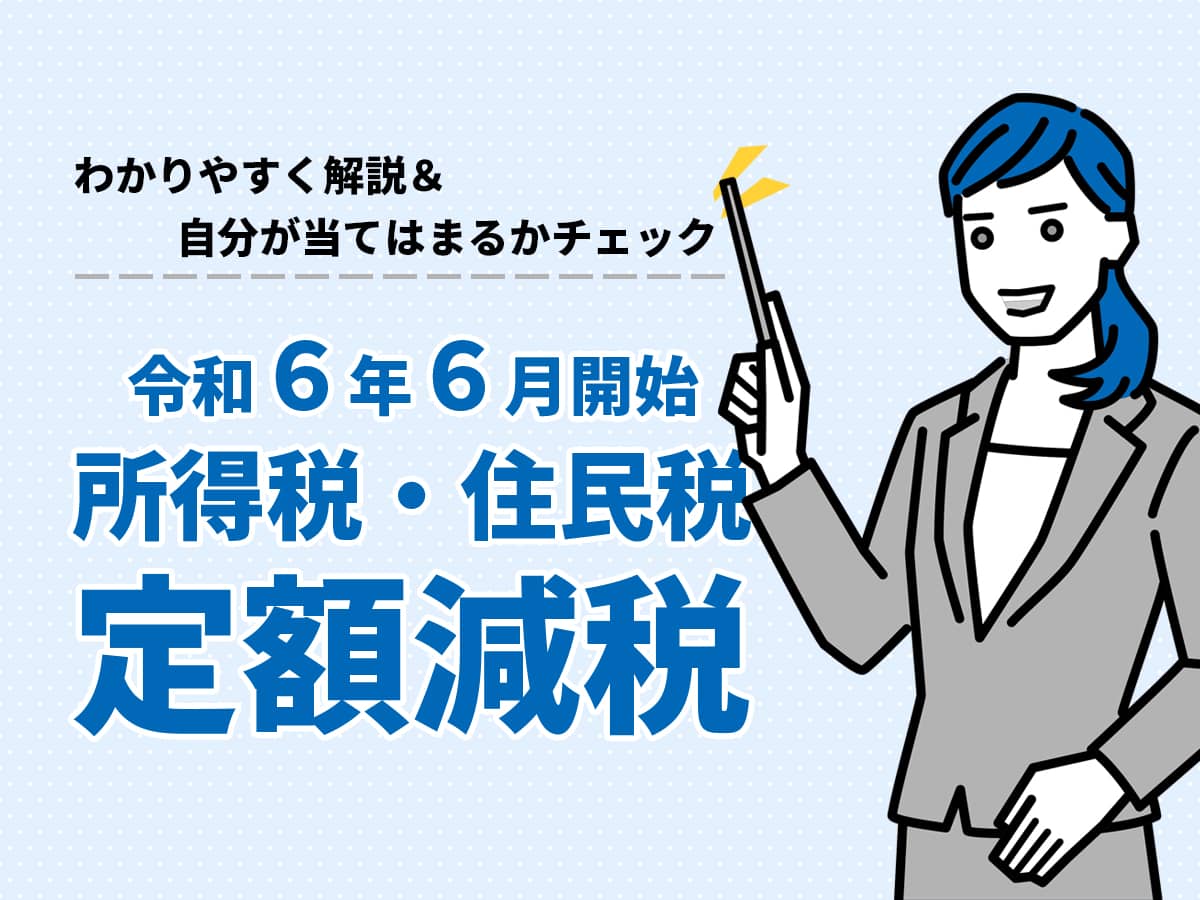
昨今の物価高などに対応するため、所得税・住民税の定額減税が2024年6月から開始されます。
しかし家族構成や働き方によって扱いが異なるため、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では所得税・住民税の定額減税についてわかりやすく解説し、自分がどういった対象なのかチェックできるようにまとめています!
定額減税とは?控除ってなに?
定額減税とは、納税額から一律に一定額を控除する制度のこと。
控除は「金額を差し引く」という意味で、税の控除にはたくさんの種類がありますが、ここでは「払うべき税金から一定金額が差し引かれる」という理解で問題ありません。
今回の定額減税では所得税が3万円、住民税が1万円の控除を受けられます。ただし令和5年の所得金額などによって減税対象外の人もいます。
ややこしい!働き方による適用方法の違い

「税金が一定金額が差し引かれるなら簡単じゃないか!」と思われた方もいるかもしれませんね。
しかし、所得税と住民税をどのように納付しているかで定額減税の方法も変わってしまいます。
大きくは「会社員の場合」と「個人事業者の場合」で異なり、それぞれを解説していきます。
会社員(給与所得者)の場合
給与所得者は所得税を会社から源泉徴収されています(いわゆる”給料からの天引き”の一種)。よって所得税の定額減税は「給料から天引きされる金額が減る」ということになります。
今回の定額減税ではまず6月に控除が行われ、控除しきれない場合は翌月以降や年末調整で控除が行われます。
住民税についても納税額が月割りで給与から天引きされるのが一般的です(これを住民税の特別徴収と呼びます)。今回の定額減税では6月分の特別徴収が行われず、7月以降の11ヶ月間で残りの住民税を月割りで払うことになります。
よって、会社の経理担当の方は対応が大変ですが従業員の方が何か特別なことを行う必要はありません。
個人事業者の場合
会社に属さない「個人事業主」や「フリーランス」という方は課税の対象となる年の翌年に確定申告で納税額が決定するため、給与所得者とは定額減税の実施タイミングが異なります。
さらに、同じ個人事業者でも「予定納税の対象者かどうか」で所得税の定額減税の扱いが異なります。
予定納税とは?
予定納税とは、5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上である場合、その年の所得税の一部を7月と11月にあらかじめ納付するという制度です。
なかなかわかりづらいですが、「本来は翌年にならないと所得税額は確定しないが、前年の所得金額から一定金額の所得税が発生すると見込まれる人は同年のうちに2回に分けて所得税を前払いする」という制度です。ちなみに予定納税で結果的に「税金を払い過ぎてしまった」という場合は、確定申告で超過分が還付されます。
予定納税の対象者なら
個人事業者でかつ予定納税の対象者なら、7月の納付タイミングで3万円が減額されます(ただし、特別農業所得者の場合は11月)。控除しきれない場合は11月の納付額が減額されます。
住民税についても同じく第1期分の金額から控除され、控除しきれなかった部分は翌月以降で控除されます。
予定納税の対象者でないなら
個人事業者でかつ予定納税の対象者でない人は、確定申告のタイミングで定額減税額が控除されます。
(参考 | これで安心!定額減税)
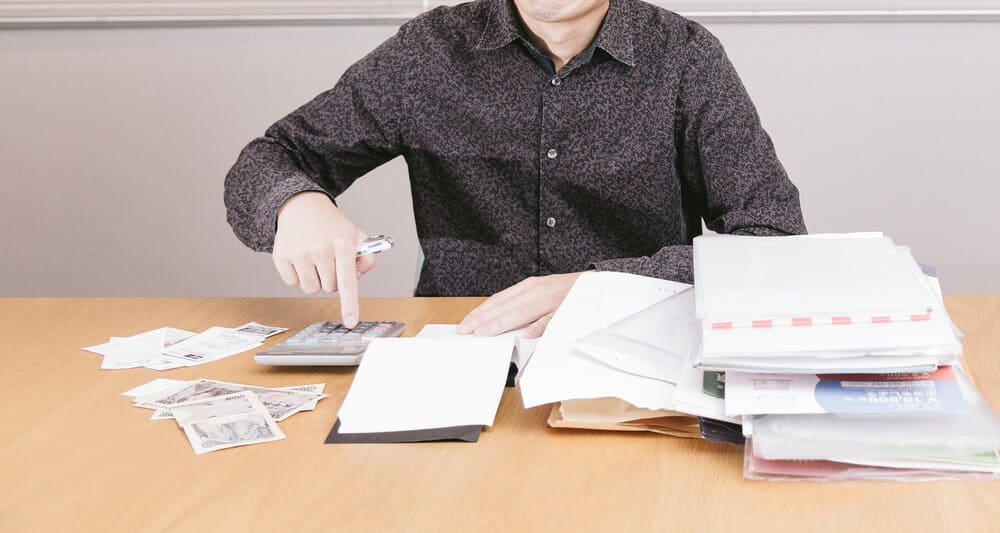
定額減税の対象とならない人は?
以下の条件に当てはまる人は定額減税の対象となりません。
- 合計所得金額が1,805万円以下を超える人※
- 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて居住が1年未満の人
※給与収入のみの場合は年収2,000万円以下が対象。「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用」を受ける方は、年収2,015万円以下までが対象です。事業所得の場合は青色申告特別控除額を引いた額で計算します。
家族分の定額減税について
納税者本人だけでなく扶養している子どもや年収103万円以下(所得が48万円)の親族らも減税の対象となります。
なお親族の所得が48万円を超える場合は対象外ではありますが、配偶者自身の所得から定額減税が行われます。
例えば夫婦と子ども2人の4人家族の場合は所得税12万円と住民税4万円の合計16万円が減税されることになります。

自分はどのように定額減税される?
さまざまな議論の末、定額減税という方法になった今回の政策。
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するためという目的はわかりつつも、ややこしいために納得感が少ない方もいるかもしれません。
こちらの記事が少しでも参考になれば幸いです!