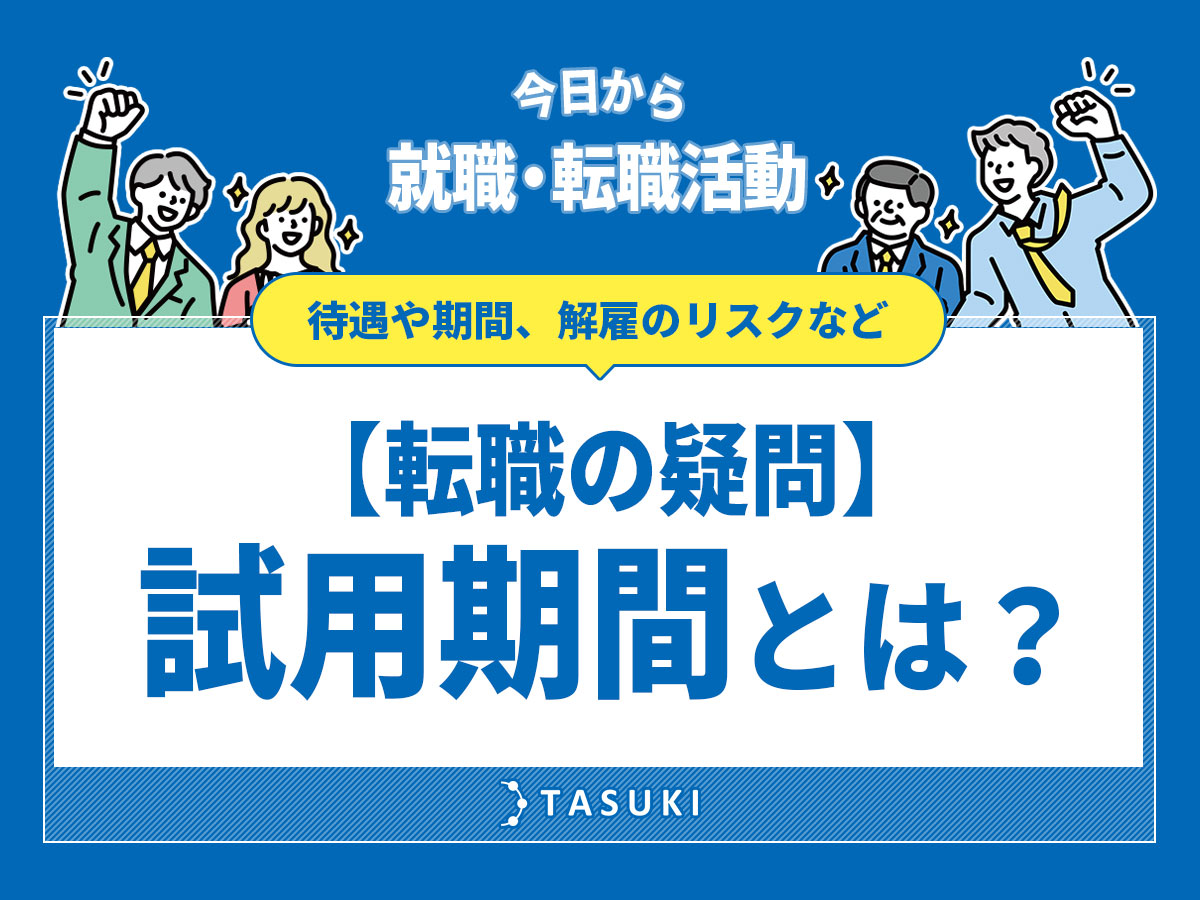
転職活動を成功させるには、入社後のミスマッチをなくすことが重要です。
そしてそのカギを握るのが、「試用期間」でしょう。
試用期間は、企業と労働者がお互いに適性を見極めるための大切な期間です。
本記事では、試用期間の概要や、期間中の待遇、解雇のリスク、退職の可否などについて詳しく解説します。
試用期間の疑問を解消し、安心して転職活動を進めるための参考にしてください。
目次
転職先での試用期間とは?
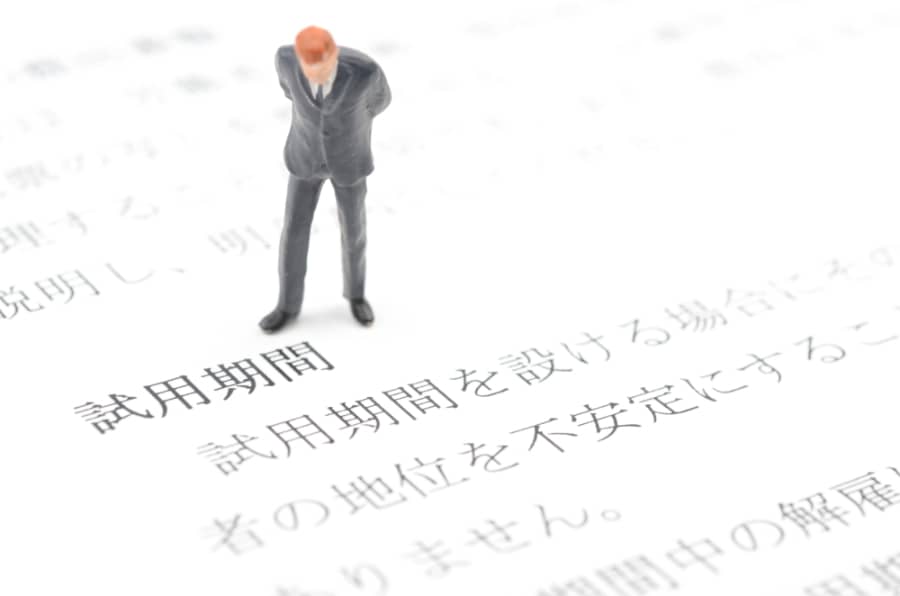
試用期間とは、いわゆる「本採用前のお試し期間」で、本採用に進む前に一定の期間を設けて、従業員の働きぶりや適性を確認するための制度です。
企業にとって、採用時の面接だけでは人柄や実際の働きぶりなどを完全に見極めるのは難しいことです。
そのため、実際に自社で業務に就いてもらいながら、業務への適性やスキル、社風への順応性などをチェックする場として試用期間が設けられています。
一般的には、試用期間の終了後、企業側と労働者側の双方が合意すれば正式な採用に至ります。
ただし、試用期間は法律で義務付けられている制度ではないため、すべての企業が導入しているわけではありません。
企業によっては、はじめから試用期間を設けず、本採用として契約を結ぶケースもあります。
転職先が試用期間を設ける目的
企業が試用期間を設ける目的は、大きく分けて2つあります。
1つ目は、採用後の企業と労働者間のミスマッチを防ぐためです。
先に紹介したように、採用面接だけでは応募者のスキルや人柄を正確に見極めるのは難しいため、実際の業務を通じて働き方や社風などとの相性を確認します。
同時に、労働者にとっても「自分に合った職場かどうか」を判断できる貴重な機会となります。
2つ目は、企業が労働者の適性を把握し、より適切な人員配置を行いやすくするためです。
企業は、試用期間で得られた情報をもとに、本人の強みや希望、適性を考慮した部署への配置を検討します。
これにより労働者が能力を発揮しやすくなり、長期的な活躍にもつながります。
試用期間と研修期間の違い
試用期間と混同されがちな言葉に「研修期間」がありますが、この2つは実施の目的や内容が異なります。
| 試用期間 | 研修期間 |
|---|---|
|
|
試用期間は、企業が労働者の能力を見極め、正式に自社の社員として迎えるか判断する期間です。
新入社員は基本的に既存社員と同様の業務にあたり、その成果や働きぶりは評価の対象となります。
一方、研修期間は業務に必要な知識や技術を身につけることが目的です。
企業や配属先の実情や方針などによって実施方法は異なりますが、座学やOJT(On the Job Training:実際に業務を行いながら仕事を覚える方法)といった形式で進められることが多い傾向にあります。
転職先での試用期間中の待遇は?

転職先に試用期間がある場合、気になるのはその待遇でしょう。
そこでこの章では、「雇用形態・労働条件」「給与やボーナス」「社会保険・労働保険」の3つの側面から確認しますので、ぜひ参考にしてください。
雇用形態・労働条件
試用期間中の雇用形態や労働条件は、基本的に本採用後と同じです。
これは試用期間が開始する前に企業と労働者のあいだで労働契約が結ばれているためで、契約内容には雇用形態や給与、勤務時間などの条件が明記されています。
労働契約自体は法律上、必ず書面で交わすことが義務付けられているわけではありません。
口頭のみでも契約は成立するものの、のちに認識の違いなどからトラブルに発展するリスクを避けるためには、文書としてしっかりと記録を残しておくほうが安心です。
給与やボーナス
試用期間中の給与は、本採用後よりも低めに設定されているケースが多いでしょう。
ただし、都道府県ごとに定められている最低賃金を下回ることは認められていません。
また、残業手当や深夜手当など法律で定められている各種手当についても、試用期間中であっても適切に支給されます。
一方、ボーナスに関しては試用期間中は支給対象外とする企業が少なくありません。
これは、ボーナスが企業の業績や個人の評価に応じて支給されるものであるためです。
勤務実績が十分に評価できない段階である試用期間中には、支給が見送られるケースが多く見られます。
社会保険・労働保険
企業には、条件を満たす従業員を社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(雇用保険・労災保険)に加入させる義務があります。
上記の取り扱いは試用期間中であっても変わらず、本採用後と同じように各種保険へ加入できます。
そのため、試用期間だからといって保険の未加入状態になる心配はありません。
転職先での試用期間に関する3つの疑問

ここからは、転職先での試用期間に関してよく聞かれる疑問についてお答えします。
転職活動を始める前に疑問や不安を解消し、安心して活動を進められるようにしておきましょう。
疑問①試用期間の長さはどれくらい?
試用期間の長さについては、法律で具体的な期間が定められているわけではありません。
多くの企業ではおおむね3ヵ月程度に設定されることが一般的で、長い場合でも1年程度が目安とされています。
また、試用期間は入社時に交わす労働契約であらかじめ取り決められているため、企業が一方的に延長することはできません。
仮に期間を延長する場合には、合理的な理由があることに加え、企業と労働者双方の合意が必要となります。
疑問②試用期間中に解雇されることはある?
試用期間を実施するにあたり、企業と労働者のあいだでは長期雇用を前提とした労働契約が結ばれていることが一般的です。
そのため、試用期間中であっても、正当な理由がなければ企業側が一方的に労働者を解雇することはできません。
解雇の正当な理由として認められるケースは、経歴詐称や著しい勤務態度の悪さ、無断欠勤などです。
また、試用期間中の解雇であっても、通常の解雇と同じく、企業側には「解雇の30日前までの予告」または「(解雇手当として)30日分以上の平均賃金(直前3カ月間を平均した1日分の賃金)の支払い」が義務付けられています。
ただし、試用期間開始の14日以内の解雇であれば、解雇予告や解雇手当の支払い義務は発生しません。
疑問③試用期間に退職してもよい?
企業側が一方的に解雇ができないのと同様に、労働者側も試用期間中だからといって簡単に退社できるわけではありません。
すでに雇用契約が成立していることにより、基本的には通常の退職と同じ手続きを踏む必要があります。
退職にあたっての手続きは、多くの企業で就業規則にて定められています。
また、民法第627条1項には、期間の定めのない雇用契約においては、退職を企業へ申し入れてから2週間で労働契約が終了することが記されています。
そのため退職を検討する場合は、まず就業規則を確認したうえで、遅くとも2週間前までに退職の意向を伝えるようにしましょう。
なかには、「雇用期間中に退職すると、次の転職で不利になるのでは?」と心配する人もいるでしょう。
試用期間中の退職が次の転職活動に影響するかどうかは、次に受ける企業の捉え方によって異なります。
そのため転職先で退職理由を面接で聞かれた際には、ネガティブな理由ではなく、次に向けた前向きな退職であったことを論理的にアピールすることが重要です。
まとめ:求人サイトで事前に転職先の試用期間の有無や期間中の待遇をよく確認しながら転職先を探そう!
転職における試用期間とは、企業にも労働者にとっても本採用前に適性などを見極める大切な期間です。
試用期間中も正社員と同様の労働契約が結ばれているため、雇用形態や社会保険、労働保険の扱いは、本採用後と基本的には変わりません。
しかし、本採用後よりも給与が少なかったり、ボーナスが支給されなかったりする場合があります。
また、試用期間は企業側も労働者側も簡単に解雇・退職することはできません。
入社後のミスマッチを防ぐためにも、試用期間の有無を事前に確認することは重要です。
転職活動の際には、求人サイトなどを活用し、試用期間の有無や期間中の待遇をよく確認しながら転職先を探すようにしましょう。