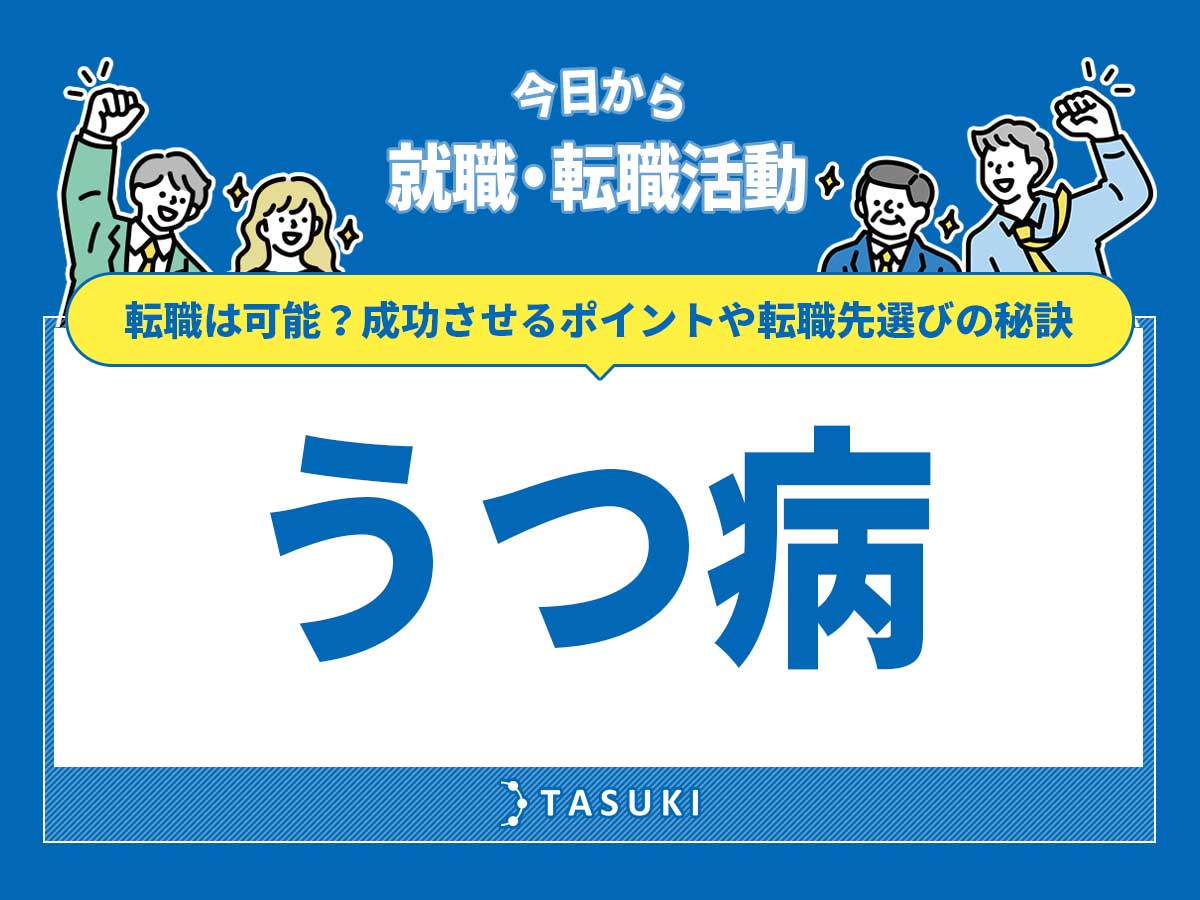
「うつ病からの転職は可能?」そう不安に思っている方も多いでしょう。また、どのように転職活動を進めてよいか分からず、一歩踏み出せずにいるケースも少なくないかもしれません。
そこで本記事では、うつ病からの転職を成功させるためのポイントや、職場先選びの秘訣、活用できる支援機関などを解説します。ぜひ、うつ病からの転職にお役立てください。
目次
【結論】うつ病からの転職は可能!

結論からいうと、うつ病の症状が回復し、安定している状態であるなら、転職は可能です。また、うつ病の方が転職しやすいような制度や、社会の受け入れ体制の整備も進んでいます。
そこでまずは、うつ病からの転職を目指すなら知っておきたい現状を解説します。
障害者雇用で就労する選択肢もある
うつ病からの転職では、一般雇用枠での就労も可能です。加えて障害者手帳を取得した場合は、さらに働き方の選択肢が増えます。
うつ病の発症によって社会生活や日常生活に制限が生じているような場合、精神障害者保健福祉手帳の取得対象となる可能性があります。障害者手帳を取得することで、障害者雇用枠での就労が可能となるのです。
障害者雇用を選択すれば、企業から業務内容や勤務時間などについて合理的配慮を受けながら働けるようになります。そのため、一般雇用と比較すると就労による心身への負担を軽減できる可能性が高いでしょう。
また、自身の体調や症状に合わせた働き方が選べれば、安心して長く働ける環境をより見つけやすくなります。
民間企業に雇用されている障害者数は増加傾向にある
現在、民間企業で働く障害者の数が増加傾向にある点も、うつ病からの転職を目指す方にとってよいニュースではないでしょうか。
民間企業の障害者枠で雇用されている人数は令和5年6月1日時点で64.2万人となっており、20年連続で過去最高を更新しています。これは、企業側の障害者雇用に対する理解が進んでいることの表れとも捉えられるでしょう。
参考:厚生労働省|障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~
法定雇用率も段階的に引き上げられている
「法定雇用率」とは、従業員数が一定規模以上の企業に対して、障害者を一定割合以上雇用することを義務づけた制度のことです。法定雇用率を満たさない企業には、納付金の徴収などの措置が取られます。
参考:厚生労働省:事業主の方へ
また、近年の法定雇用率の推移は以下のとおりです。
- 1999〜2012年:1.8%
- 2013〜2017年:2.0%
- 2018〜2020年:2.2%
- 2021年~2023年:2.3%
- 2024年~:2.5%(現在)
- 2026年~:2.7%(予定)
参考:独立行政法人労働政策研究・研修機構|図16 障害者雇用状況の推移
:厚生労働省|令和5年度からの障害者雇用率の設定等について
上記からもわかるように、法定雇用率は段階的に引き上げられており、企業の障害者雇用への意識は高まっているといえるでしょう。この点も、うつ病からの転職を検討するうえでは追い風になると考えられます。
うつ病から転職する方法は2通り

うつ病から転職活動を行う際には、2つの方法があります。それぞれの特徴を紹介しますので、自分にあった方法はどちらか検討してみてください。
方法①うつ病で休職中に転職活動を行う
「うつ病で休職中に転職活動をしてよいのか」と思われる方もいるかもしれませんが、休職中の転職活動自体に法的問題はありません。しかし、うつ病の治療を継続している場合は無理に転職活動を進めてしまうと症状が悪化するおそれがあるため、慎重な判断が求められます。
転職活動を行っても問題がないかどうかを主治医に確認するようにしましょう。
方法②退職後に転職活動を開始する
退職後に転職活動を始める場合、雇用保険の失業手当を受給しながら、じっくりと仕事探しができる点がメリットです。ただし、退職すると自分で健康保険や年金の切り替え手続きを行う必要が生じます。
また、収入が途絶えるため、生活費を考慮しながら計画的に転職活動を行うことなるでしょう。
うつ病からの転職で押さえておきたい5つのポイント

ここからは、うつ病からの転職に向けて重要となるポイントを紹介します。
主なポイントは、以下の5つです。
- うつ病の治療は続けること
- 生活リズムを整えること
- ひとりで決断しないこと
- 自己分析を行うこと
- 働き方を見直すこと
それぞれ詳しく確認していきましょう。
ポイント①うつ病の治療は続けること
うつ病の治療中に転職活動を行う場合、自己判断で治療を中断したり、薬をやめたりすることは避けましょう。再発や症状悪化のリスクが高まるだけでなく、転職活動にも悪影響を及ぼすおそれがあります。
医療機関と連携しながら転職活動を行うことで、体調を安定させつつ新生活へとスムーズに移行しやすくなります。
ポイント②生活リズムを整えること
心身を安定させるためには、規則正しい生活が不可欠です。体内時計が整うことで、幸せホルモンとも呼ばれる「セロトニン」の分泌が促され、前向きな気持ちを保ちやすくなるといわれています。
これまでの疲れなどを癒すためにも、十分な睡眠と休息を心がけ、心身のバランスを整えましょう。安定した生活リズムが、スムーズな転職活動をもたらします。
ポイント③ひとりで決断しないこと
うつ病の症状が強く出ているときは、客観的な判断が難しくなりがちです。一人で悩んでいると、悲観的な考えに陥ったり、視野が狭まり、焦って後悔につながるような決断をしてしまったりするかもしれません。
信頼できる家族や友人、主治医などに相談することで、冷静な視点を得られます。多角的な意見を取り入れながら、納得のいく転職を実現しましょう。
ポイント④自己分析を行うこと
転職活動を始める前に、自己分析を行いましょう。過去の経験から、自分はどのような状況でストレスを感じやすいのか、また、そういった際に表れやすい兆候などを把握することが重要です。
ストレスへの対処法や再発防止策を事前に考えておくことで、安心して新しい環境へ臨めるようになります。
ポイント⑤働き方を見直すこと
うつ病の治療が進むにつれて、自分に合った対処法や生活スタイルが見えてくるでしょう。それらを踏まえ、自分にとって最適な働き方を改めて検討することが大切です。
勤務時間や業務内容などを見直し、柔軟な働き方を模索することで、長く活躍できる道が開けます。
うつ病からの転職を成功に導く職場の選び方

うつ病を抱えながらも働きやすい職場を選べば、転職後に長く働ける可能性が高まります。ここでは、うつ病からの転職を成功させやすい職場の選び方を紹介します。
自分に合った働き方ができるか
うつ病からの転職では、柔軟な勤務形態が可能な職場を選ぶことが重要です。自分のペースで働ける環境か、勤務時間や場所の融通が利くかを確認しましょう。
また、先に紹介したように障害者雇用枠での転職も視野に入れると、より働きやすい職場を見つけやすくなります。
サポート体制は整っているか
うつ病からの転職では、企業側のサポート体制が充実しているかどうかの確認も欠かせません。産業医やカウンセラーの配置、メンタルヘルスに関する研修制度、休職・復職支援制度などが整備されていると、安心して働きやすいでしょう。
特に障害者雇用枠での転職を検討する場合は、企業側の理解や配慮、サポート体制の有無が働きやすさに大きな影響を及ぼします。
うつ病からの転職で活用できる支援機関

うつ病からの転職を成功させるためには、さまざまな支援機関を活用することが有効です。うつ病からの転職で活用できる支援機関は、主に以下のようなものが挙げられます。
- ハローワーク:専門の相談員が求人情報の提供や職業相談を実施
- 地域障害者職業センター:職業リハビリテーションや職場復帰支援など、専門的なサポートを提供
- 就労移行支援事業所:就職に必要なスキルや知識を習得するための訓練を実施
- 精神保健福祉センター:心の健康に関する相談や情報提供
- 転職エージェント:個別のニーズに合わせた求人紹介や面接対策など、手厚いサポートを提供
また、自分に合った働き方や転職先の条件が明確になっている場合は、求人サイトで条件を絞り込んで検索するのも手でしょう。
さまざまな選択肢を組み合わせることで、より自分に合った転職先を見つけられる可能性が広がります。
まとめ:自分に合った働き方が把握できたら、求人サイトを活用して転職先を探してみよう!
うつ病からの転職は、決して不可能なことではありません。新たな環境に踏み出すことで、病状の改善につながるケースもあります。
ただし、心身の安定を図りながら、焦らず転職を実現していくことが大切です。
まずは、自己分析を通じて自分に合った働き方を把握しましょう。そのうえで、求人サイトなどを活用しながら条件に合った転職先を探してみてください。