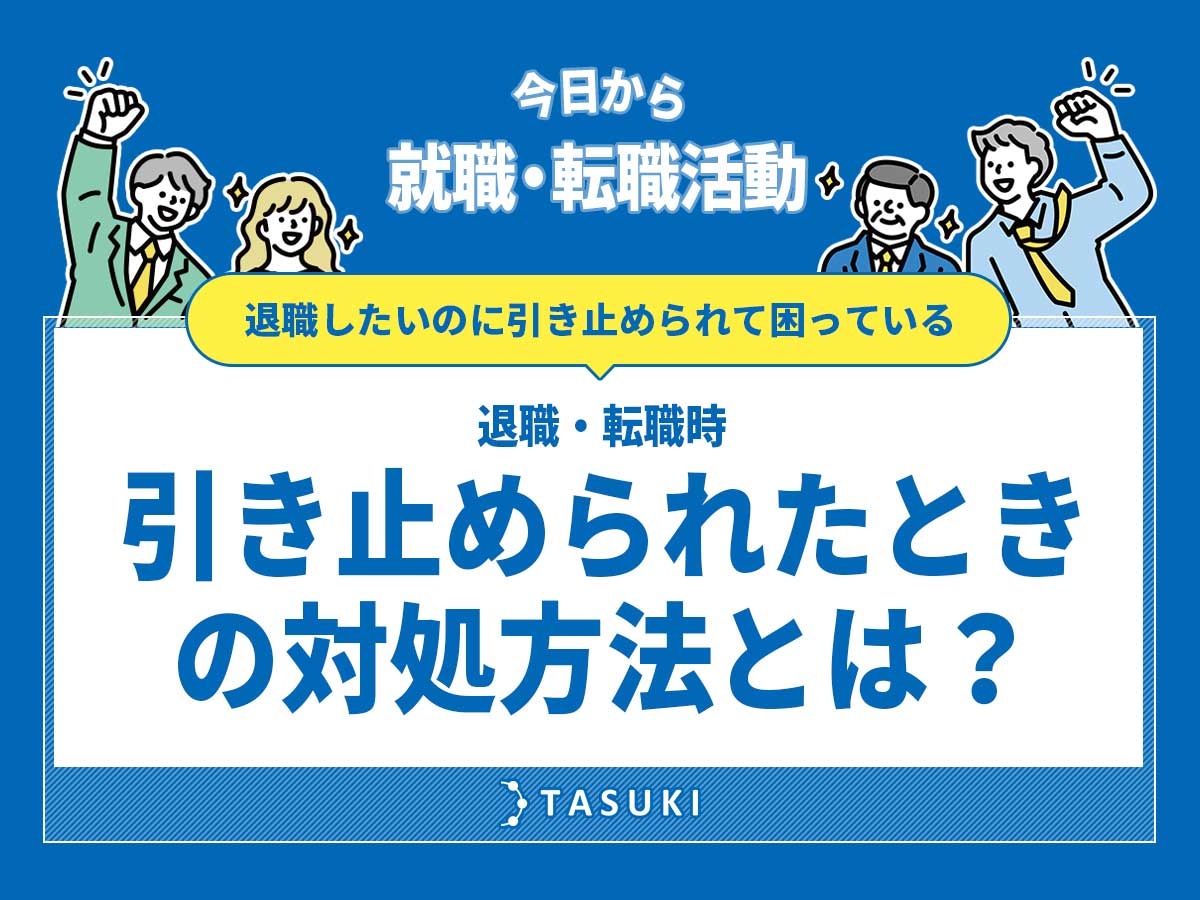
「退職したいのに引き止められて困っている」そんな経験はありませんか。転職や退職を決意しても、会社からの引き止めによってスムーズに進まないケースは珍しくありません。人材不足や優秀な人材を手放したくないという理由のほか、「あなたのため」と親身を装った引き止めも存在します。しかし、退職の自由は法律上の権利であり、申し出から2週間で成立します。
本記事では、引き止められた際の具体的なパターンとその対処法、円満退職に向けた準備のポイントまでを解説します。冷静に、かつ誠実に対応するための知識を身につけましょう。
目次
退職・転職希望者を引き止める理由
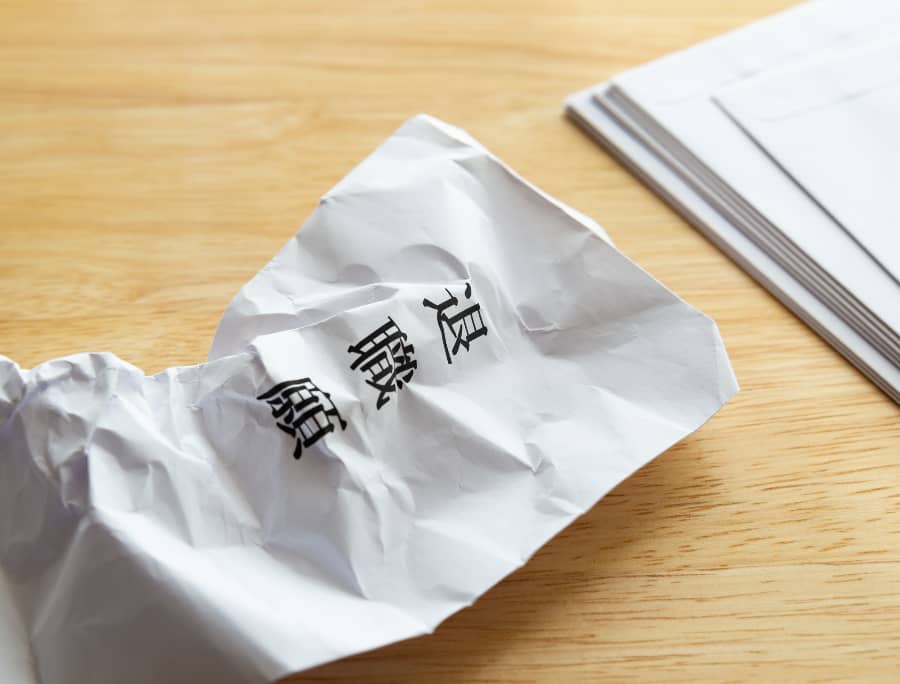
会社が退職・転職希望者を引き止める理由は3つあります。
- 会社が人材不足だから
- 優秀な人材を手放したくないから
- 本人のためを思っているから
それぞれ解説します。
会社が人材不足だから
人手不足が深刻な会社では、人手不足が理由で引き止められることがあります。特に中小企業や特定の専門職では、退職者の穴を埋めることが困難です。新たな人を採用しても、採用と育成に時間がかかるため即戦力にはなりにくいです。その結果、今いる社員に頼らざるを得ない状況が生まれます。
人材不足は組織全体の生産性や士気にも影響を及ぼすため、企業は退職を防ぐために必死になります。現場の状況次第では、退職希望者に過剰な引き止めが行われる可能性もあります。
優秀な人材を手放したくないから
優秀な人材は、会社の利益や業績に大きく貢献します。一度現場にフィットした人材を一から探すのは難しく、会社としては手放したくないのが本音です。高いスキルや豊富な経験、社内での信頼関係は短期間では再構築できません。人材市場の流れも激しく、同等の能力を持つ人材を採用できる保証はありません。そのため、企業は退職の意思が示された段階で引き止めに入ることが多いです。給与や待遇の見直し、役職の提案などを通じて残留を促します。企業にとって、優秀な人材は戦力であると同時に資産でもあります。
本人のためを思っているから
引き止めの際に「あなたのため」と言われることがあります。転職や退職にはリスクが伴うため、本人が失敗しないようにという配慮からです。上司は多くの経験を重ねており、過去の事例を踏まえたうえで忠告することもあります。その判断が正しい場合もあるため、引き止めの言葉を一度は冷静に受け止めることも必要です。
しかし、すべてが善意とは限りません。本人の成長や希望よりも、会社の戦力を維持したいという思惑が背景にある場合もあります。表向きは親身な態度をとりつつ、実際は引き止めることで自らの業務負担を減らしたいと考えている上司もいるため、見極めが重要です。
引き止められる時のパターンと対処方法

引き止められた時のパターンと対処法は主に5つあります。
- 待遇改善による引き止め
- 会社の損失を理由に引き止める
- 引き継ぎ期間を理由に引き止め
- 転職のリスクで不安を煽って引き止め
- 退職に応じない
- 退職の相談は1か月以上前にしておく
- 退職・転職理由を明確にする
- 引き止められて退職できないのは違法?
- 引き止めで心が揺らぐときの対処法は?
詳しく解説します。
待遇改善による引き止め
給料を上げる、部署移動を検討する、働き方を柔軟にするなど待遇改善を提案されるかもしれません。その場合には、なぜ今まで改善されなかったのか、具体的な内容はどうなのかを上司に確認して残った方がメリットがあるのか考えましょう。提案が本当に実行される保証があるかを見極めることも重要です。曖昧な口約束や期限のない改善策には注意が必要です。改善が一時的な引き止め策であれば、再び同じ問題が発生する可能性があります。
会社の損失を理由に引き止める
引き止めの中でも多いのが「あなたが辞めると会社にとって損失だ」という理由です。人員不足や業務の属人化が進んでいる場合、「辞めると手が回らない」「他の仲間が忙しくなって迷惑をかけてしまう」と説得される可能性があります。
ですが、これらは本来、会社の経営課題であり、社員個人が背負うものではありません。自分の将来やキャリアを犠牲にしてまで現状にとどまる必要はありません。相手の事情を理解しつつも、冷静に自分の考えを貫くことが重要です。引き継ぎや業務整理を丁寧に行い、自分の責任を果たす姿勢を示すと円満退職につながります。
引き継ぎ期間を理由に引き止め
引き継ぎ期間が足りないからという理由で引き止められた場合、会社に迷惑はかけてしまうものの、引き継ぎは会社が対応することでもあると上司に説明しましょう。退職者がすべてを担う責任はありません。
事前に引き継ぎのスケジュールを立てておくと、上司にも納得のいく説明ができます。引き継ぎ資料や業務マニュアルを用意し、必要な業務の洗い出しを行うことで、円滑な移行が可能です。誠意ある対応を心がけることで、過度な引き止めを避けることができます。
転職のリスクで不安を煽って引き止め
引き止めの中で多いのが、転職のリスクを強調して不安をあおるパターンです。「どこも同じだ」「うまくいかないかもしれない」など、転職後の不確実性を強調する発言をされます。確かに不安は付き物ですが、自分なりに考えて決めた道だとしっかり伝えましょう。不安に揺さぶられたまま残ると、後悔や不満が溜まる可能性があります。転職先の情報収集や準備を十分に行い、自信を持って決断したと説明するのが大切です。相手の意見を否定せず、感謝の気持ちを伝えた上で退職の意思を変えない姿勢を示すと、冷静に対話が進みやすくなります。
退職に応じない
退職自体を拒否される場合があります。上司が「認めない」と主張することもあります。その場合は、さらに上の上司に相談してみましょう。それでも受け入れてもらえない場合、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
法律的には民法627条により、退職の申し出から2週間経過すれば退職は成立するため、会社の同意は不要です。法的な手段を検討することで、精神的な負担も軽減されます。自己判断で辞めることに不安がある場合は、専門機関の助言を早めに受けることをおすすめします。
トラブルを避けて転職・退職するには

トラブルを避けるには以下の2点が大切です。
詳しく解説します。
退職の相談は1か月以上前にしておく
退職の意思を伝えるタイミングは非常に重要です。法律上は2週間前の申し出で退職できますが、最低でも1か月以上前に相談するのが適切です。早めに相談することで、引き継ぎや後任の選定がスムーズに進み、職場の混乱を防げます。急な退職は同僚の負担を増やし、信頼関係の悪化を招く恐れもあります。
また、就業規則で「1か月前」や「2か月前」など具体的な期日が定められている場合もあります。その場合は規則に従った方が円満退職しやすいです。直属の上司にまずは相談し、その後正式な手続きを踏むことで、トラブルを未然に防げます。
退職・転職理由を明確にする
円満に退職・転職を進めるためには、まず自分の退職理由や転職の目的を明確にしておくことが大切です。理由が曖昧なままだと、引き止めや誤解を招く可能性が高くなり、職場との関係がこじれる原因にもなります。
例えば「スキルアップを目指したい」「家庭の事情で働き方を変えたい」など、前向きかつ具体的な理由が望ましいです。明確な理由を準備しておけば、相手の理解も得やすくなります。
引き止めについてよくある質問

引き止めについてよくある質問を2つ紹介します。
それぞれ解説します。
引き止められて退職できないのは違法?
労働者が退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社側が一方的に引き止めて退職させないことは、原則として違法行為にあたります。法律では、期間の定めのない雇用契約の場合、労働者は退職の意思表示から2週間で退職が成立すると定められています。そのため、合意がなくても退職は有効です。強制的な引き止めには応じる必要はありません。
引き止めで心が揺らぐときの対処法は?
迷いが生じた場合は、一度立ち止まって退職理由を再確認します。退職を決める上で一番優先したいこと、退職理由は会社に残って解決できることではないかなどを改めて明確にします。信頼できる第三者に相談するのも有効です。一時的な感情に流されず、自分にとって最良の選択を見極めます。
退職を引き止められた場合も冷静に対処しましょう

退職や転職時には、会社から様々な理由で引き止められることがあります。主な理由は、人手不足、優秀な人材の流出防止、本人の将来を心配する善意などです。対処法としては、待遇改善の提案に対してその実現性を見極める、会社の損失や引き継ぎ期間を理由にした説得には冷静に応じる、転職リスクを過度に強調された場合は自分の決断に自信を持つことが重要です。
仮に退職自体を拒否されても、民法627条により2週間前の申し出で退職は成立します。早期相談や明確な理由を提示しておくことが円満退職に繋がります。心が揺れる場合も感情ではなく目的を再確認し、第三者に相談するなどして冷静な判断を心がけましょう。