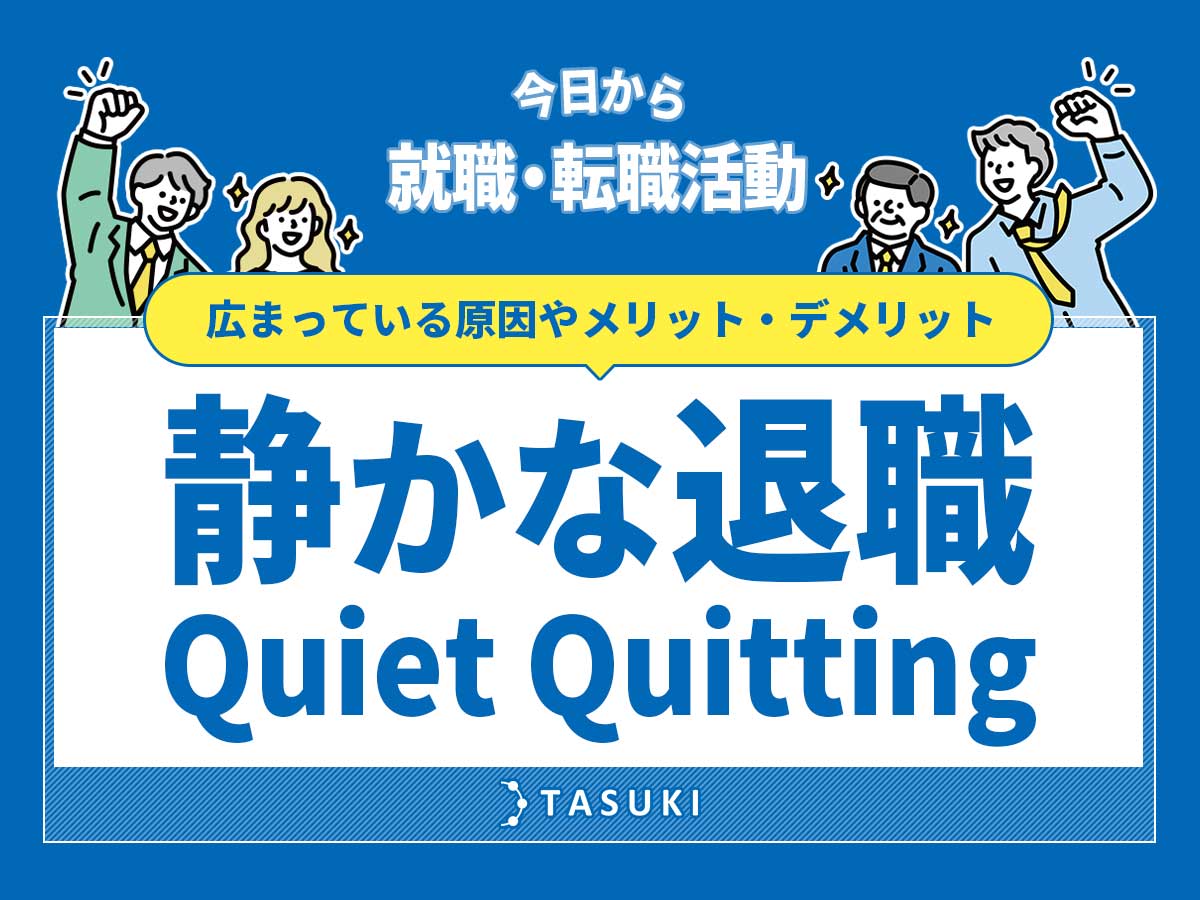
毎日の業務に追われ「評価もされないのに頑張る意味があるのか?」と疑問を感じたことはありませんか。多くの人が同じように悩み、あえて出世や成果を求めない「静かな退職(Quiet Quitting)」の選択をするようになっています。静かな退職は、ただの怠慢ではなく、自分の時間やメンタルを守る防衛手段ともいえます。
本記事では、静かな退職が広がっている背景や、そのメリット・デメリットを分かりやすく解説します。
目次
静かな退職(Quiet Quitting)とは?

静かな退職(Quiet Quitting)とは、表面的には退職せずに勤務を続けているものの、仕事に対する積極性や熱意が薄れており、与えられた業務だけを淡々とこなす働き方です。転職や退職の意思はなく、勤務時間中に最低限の業務をこなし、それ以上の努力や自主的な仕事は避ける傾向があります。
本人にとっては過剰なストレスを避ける手段ですが、企業側から見ると「やる気のない社員」と見なされやすいです。そのため、静かな退職が長期化すると、会社の業績が傾いた際には整理解雇(リストラ)の対象となるリスクもあります。
静かな退職は、心身の疲労や職場環境の悪化、人間関係のストレスなどが背景にある場合も多く、放置すると本人のキャリアや職場全体の生産性にも悪影響を及ぼします。
静かな退職(Quiet Quitting)のやり方

静かな退職(Quiet Quitting)のやり方は、責任のある仕事は断る、時間外の業務は対応しない、スキルアップや昇進を目指した努力は行わない、研修会や勉強会にも参加しないなどが挙げられます。
あくまで就業規則や契約に沿った業務に専念し、成果や評価にこだわらない姿勢です。静かな退職は、無理な目標設定や過剰な働き方に疑問を持つ人が、精神的な安定や生活の質を重視するために選ぶ行動です。最低限の仕事はしつつ、離職ではなく現状維持を目指します。
静かな退職(Quiet Quitting)が広まっている原因

静かな退職が広まっている原因として、以下の2つが挙げられます。
- 仕事に対する価値観の変化
- 燃え尽き症候群の影響
それぞれ解説します。
仕事に対する価値観の変化
静かな退職が広まっている背景には、仕事に対する価値観の変化があります。かつては仕事一筋で長時間働くことが美徳とされていました。努力や根性で成果を出すことが重視され、プライベートを犠牲にするのが当然の環境です。
しかし、現代では仕事よりもワークライフバランスを大切にする人が増えています。働く目的が生活のためであり、健康、家庭との両立を重視する傾向が強いです。その結果、仕事は必要最低限の責任を果たす範囲にとどめ、残業や休日出勤を避け、趣味や休息に時間を充てる人が多くなっています。
キャリアよりも人生全体の充実度を優先する考え方が広がり、昇進や出世にこだわらない人も少なくないです。その結果、静かな退職という行動が一つの働き方として広がりつつあります。
燃え尽き症候群の影響
燃え尽き症候群は、静かな退職が広まっている要因の一つです。仕事に全力で取り組んできたにもかかわらず、成果が正当に評価されなかったり、昇給や昇進につながらなかったりする状況が続くと、従業員は徐々に精神的な疲労が蓄積します。その結果、意欲や熱意が失われ、心身ともに限界を迎えます。
こうした状態に陥ると、多くの人は仕事に対しての期待や希望を失い、与えられた最低限の業務だけをこなす静かな退職という働き方を選びやすいです。表向きには職場に留まりつつも、積極的に成果を求めることはなくなります。
静かな退職は、決して怠惰ではなく、自分自身を守るための消極的な自己防衛です。評価されない努力や報われない労働が続けば、誰しも心が折れます。燃え尽きた心と向き合いながら、仕事をするための防衛手段となっているのが現状です。
静かな退職(Quiet Quitting)によるメリット

静かな退職によるメリットは2つあります。
- ストレスが減ってメンタルが安定する
- 自分の時間を確保しやすい
詳しく解説します。
ストレスが減ってメンタルが安定する
静かな退職を選ぶことで、過剰な業務やプレッシャーから解放されてメンタルが安定します。無理な残業や休日出勤を避けると本来の業務範囲に集中できるため、心身への負担が軽減し、ストレスが大幅に減少します。ストレスが原因となるうつ病や不安障害などのメンタル不調の予防にもつながるでしょう。
また、プライベートの時間を確保しやすくなるため、趣味や休息を通じて気持ちをリセットできる機会が増えます。こうした心の余裕が、自己肯定感やモチベーションの回復にもつながります。メンタルの安定は仕事をするうえでの土台となるため、長期的なキャリア維持にも効果的です。
自分の時間を確保しやすい
静かな退職では、必要以上の業務を行わないため、残業や休日出勤が減り、自分の時間を確保しやすいです。その結果、退勤後に趣味や家族との時間を楽しむことができ、心身のリフレッシュにもつながります。
リモートワークやフレックスタイムが浸透する現在、業務範囲の線引きを明確にすることは、ワークライフバランスを保つうえで重要です。静かな退職は、自分の時間を守る有効な手段の一つといえます。
静かな退職(Quiet Quitting)によるデメリット

静かな退職によるデメリットは3つあります。
- 整理解雇にあうリスクが増加する
- 職場全体の士気・生産性が低下する
- 従業員自身が成長する機会が失われる
それぞれ解説します。
業績悪化時に整理解雇(リストラ)されるリスクが増加する
静かな退職は、会社の業績悪化時に整理解雇(リストラ)の対象となるリスクが伴います。目立った成果や積極性が見られない場合、会社側から「必要性の低い人材」と判断されやすいためです。会社の業績に問題がなく雇用され続けた場合でも、評価が低くなり昇進や昇給のチャンスを逃しやすくなります。
短期的には精神的な安定を得られるかもしれませんが、キャリアの選択肢や働く環境の質を自ら狭める行動になりかねません。自分の将来を守るためには、積極的に仕事をする姿勢や成果への意識も重要です。
職場全体の士気・生産性が低下する
静かな退職をする社員が増えると、職場の士気や生産性が低下します。一部の社員が「与えられた仕事だけをこなす」姿勢になると、他のメンバーにしわ寄せが及び、業務負担が偏ります。頑張る人ほど負担が重くなり、不満や疲労が蓄積しやすいです。やる気を失う社員が増えれば、チーム全体のモチベーションが下がります。
結果的に、全体の生産性が落ち、目標達成や業績にも悪影響を与える可能性があります。このように個人の意識が職場全体に波及し、組織の力を弱めてしまうリスクが高いです。
従業員自身が成長する機会が失われる
静かな退職によって、従業員は成長の機会を自ら手放すことになります。与えられた最低限の業務だけをこなし、それ以上の役割や責任を引き受けない姿勢は、スキルアップのチャンスを逃しやすいです。
業務を通じて得られるはずだった経験や知識が限られ、自分の可能性を広げる機会が縮小します。また、社内での評価も上がりにくくなり、昇進などのポジティブな変化が起きにくいです。
いざ転職を考えることになったとしても、アピールできる実績が不足し、不利になる可能性があります。自ら成長の場を狭めることは、長期的なキャリア形成において大きな損失です。自分の未来を広げるためにも、積極的な姿勢が重要です。
静かな退職(Quiet Quitting)よりも将来的な成長を考えて転職しよう

静かな退職とは、与えられた業務だけをこなして、それ以上の努力をしない働き方です。一見、心身のバランスを保てる方法に見えますが、実は多くのリスクをはらんでいます。
最低限の仕事しかしない姿勢は、上司や同僚からの評価を下げます。新しいスキルを身につける機会が減り、自身の成長が止まり、結果的に将来的な収入やキャリアの幅が狭くなりがちです。また、職場の雰囲気を悪くしてしまう可能性があります。
もし現職での成長が難しいと感じるなら、将来的な可能性を見据えて転職を検討するのも選択肢の一つです。ワークライフバランスや自分のメンタルを大切にしながらも、いち社会人として成長できる環境に身をおくのがベストではないでしょうか。