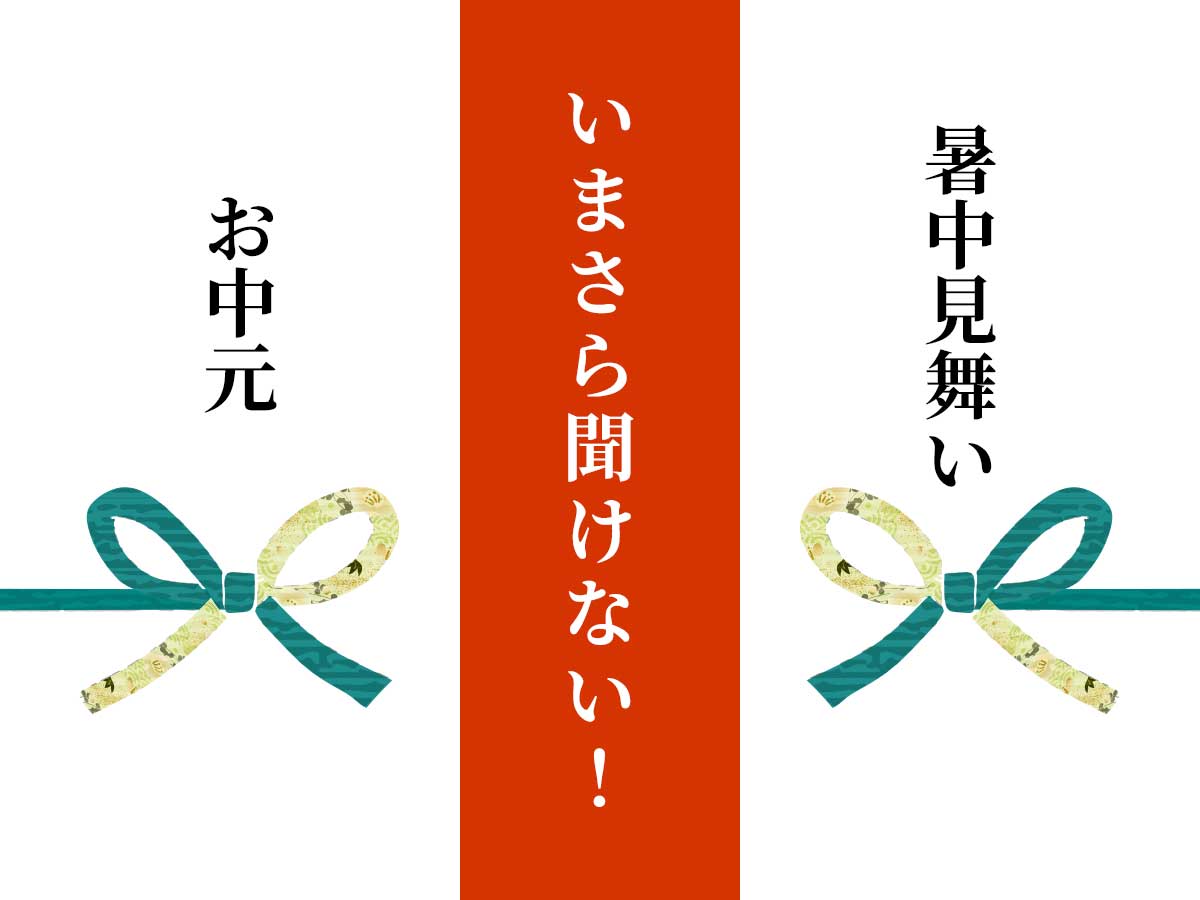
汗ばむ日も多くなってきましたね。夏が近づいてくると気になる「お中元」と「暑中見舞い」。
昔からの習慣ですが、意味や違いを知らない人も多いのではないでしょうか。
この記事では、起源や意味、時期やマナーまでわかりやすくご紹介します。
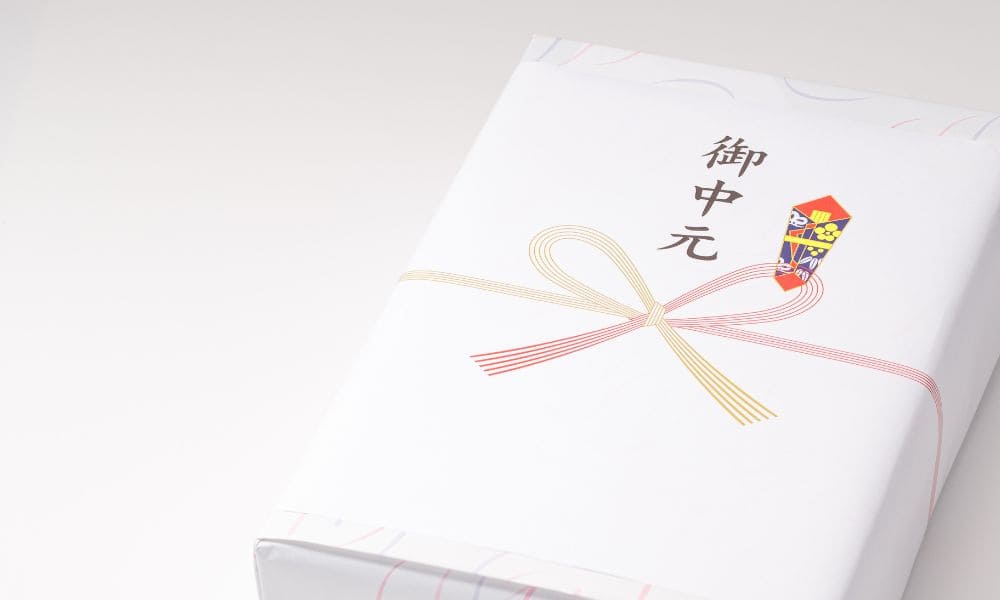
お中元と暑中見舞い、何が違うの?
なりたちや意味合い
お中元は、1年のちょうど半分の夏の時期、親族や職場関係者、恩師などお世話になった方々へ感謝の贈り物をする習慣です。
起源は、中国の旧暦7月15日の「中元節」で、これが日本の盂蘭盆会(うらぼんえ)と合わさり、現在のお中元の形になりました。一方、暑中見舞いは猛暑の時期に大切な方に贈るあいさつ状で、健康を気遣い、元気で過ごしてほしいと願いが込められています。
江戸時代、お盆に里帰りをするご先祖様の霊に備える品物を持参する習慣が、お世話になっている方への贈答として行われるようになり、現在の暑中見舞いとして定着しました。ですので、お中元は「感謝の贈り物」暑中見舞いは「大切な方へのあいさつ状」という違いがあります。
贈るタイミング
お中元は、一般的には7月上旬から7月15日頃までとされています。西日本では7月中旬から8月15日ごろまでという地域もありますが、お中元は上半期の感謝を贈るものですので、お盆前までに贈ることが多いです。
暑中見舞いを贈る時期は、梅雨明けの7月7日ごろから立秋の前日(8月7日ごろ)に贈るのが一般的です。実際の暑さはまだそれほどでもないのにな、と思われるかもしれませんが、暦が基準になるので、立秋前には贈るようにしましょう。立秋を過ぎてしまった場合は「残暑見舞い」として贈ります。
どちらも贈りたい場合はどうすればいい?
意味合いの異なるお中元と暑中見舞い。どちらも贈りたいと思った場合、どのようにすればいいのでしょうか。
一般的にはどちらか一方にしますが、どうしてもの場合は両方送っても大丈夫。ただし、贈る時期が近いので、相手の負担にならないように配慮が必要です。
お中元に暑中見舞いを添える形で同時に贈っても問題ありません。

相手が喪中の場合は贈ってもいいの?
日本には、喪中の期間はお祝いの贈り物を避けるという風習がありますが、お中元や暑中見舞いはお祝いの贈り物ではないので、贈るのも受け取るのも問題ありません。
ただし、心遣いは必要です。四十九日が過ぎるまでの期間は、ご家族の気持ちの整理を優先して、贈り物は避ける方が無難です。そして、喪中の方にお中元を贈る際は、紅白蝶結びの熨斗紙は避け、白地の熨斗紙を選ぶようにしましょう。
暑中見舞いを出す際は、文中にお悔やみの文章を書いたり、ハガキの絵柄を派手にしないようにします。
お中元 押さえておきたい贈る時・受け取った時のマナー
あまり高価な品だと相手に気を使わせてしまい、迷惑にもなりかねません。贈る相手との関係性にもよりますが、相場をしっかり押さえて贈るようにしましょう。親や親せきのような間柄で、だいたい3,000円から5,000円。特にお世話になった方、仕事の関係で贈る場合には3,000円から10,000円が相場だといわれています。
お中元は毎年贈り続けるものです。特別な理由なく贈り物の金額が変わったり、前年の予算より低い品物を贈ることはマナー違反と言われています。先を見据えて無理のない予算設計をするようにしましょう。
お中元を選ぶ際に気をつけたいのは、予算だけでなく、相手の好みや家族構成なども考慮するということです。例えば、お子さまのいるご家族であればゼリーやジュースのようなお子さまが喜びそうなものを、1人暮らしのかたであれば、量が多すぎず、日持ちがするものを選ぶなど、相手の立場にたって、喜んでもらえそうなものを選ぶようにしましょう。
日本の贈り物に欠かせないのし紙にも注意が必要です。のし紙は表書きに「暑中御見舞い」と書きますが、目上の方に贈る場合は「暑中お伺い」「暑中御伺い」「暑中御伺」と書いてください。水引は5本線の蝶結びを選びましょう。名前の部分は送り主の苗字を書きますが、同じ苗字の親戚などに贈る場合はフルネームを書くことをおすすめします。
お中元で送ってはいけない物4選
ハンカチ
お中元に限らず、贈り物で避けたいのはハンカチです。手切れ(手布)を連想させるところから、「あなたにはもう会いたくないです。」と連想してしまう可能性があるので、避けた方が無難です。
花
お花自体を贈ることはマナー違反ではありませんが、お花の種類に気をつけましょう。つつじなど、首から落ちる花は「死」を連想するので、贈り物にはふさわしくありません。花言葉にも注意が必要です。
刃物
料理好きな方への贈り物にキッチン用品を贈ることはありますが、包丁やはさみなどの刃物は避けましょう。刃物は「切れる」ことから「縁を切る」を連想させますので、「これからもよろしくお願いします」の意味を持つお中元には不向きと言えます。
履物・下着
男性への贈り物として人気がある下着や靴下は、「着るものに困っているから恵んであげる」や「踏みつける」を連想するので、お中元だけでなく、贈り物にはむいていません。特に、年上の方に対して履物や下着を贈るのは大変失礼に当たるので、避けましょう。
暑中見舞いの書き方
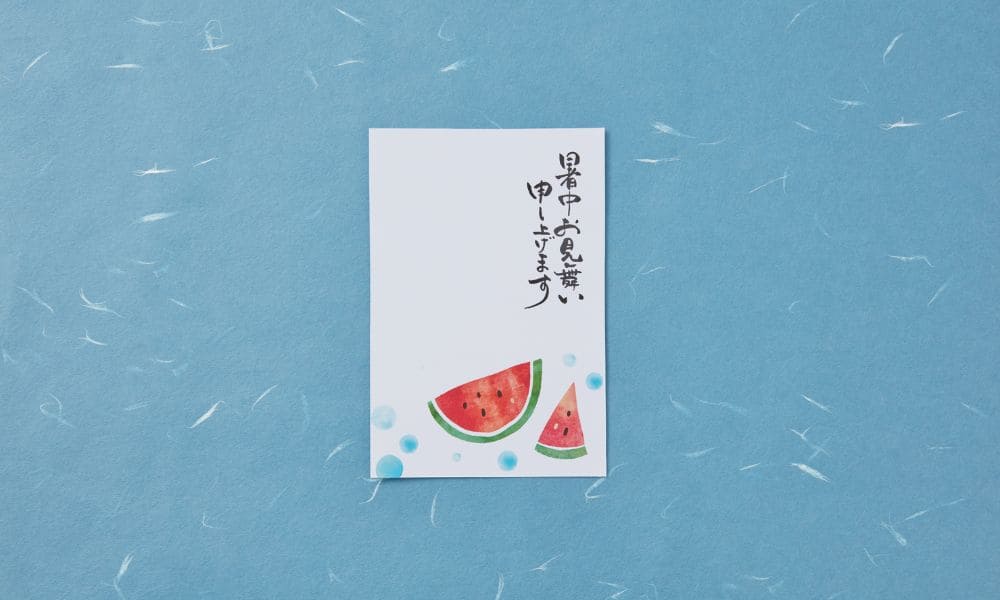
暑中見舞いは、以下の構成で書かれています。構成に沿い、お好きな言葉であなたらしい暑中見舞いのハガキを書いてみましょう。
お見舞いのあいさつ
「暑中お見舞い申し上げます」の文章から始まります。上司など目上の方に出すときは「暑中お伺い申し上げます」と書くのが一般的です。
お見舞いのあいさつ状には句点(、や。)をつけません。暑中見舞いだけでなく、年賀状などにも共通するルールですので、覚えておくと便利です。
時候のあいさつ
7月であれば「梅雨明けもして 暑さ厳しい折」「梅雨が明けたとたんに 猛烈な暑さになりましたが」「梅雨明けとともに本格的な夏がまいりましたが」など梅雨が明けて夏が来た事をあいさつとし、8月になれば、「連日猛暑がつづいておりますが」「立秋と名ばかりの暑さが続いておりますが」「盛夏の折」「猛暑の候」など、暑い日が続いていることをあいさつとし、その時期の気候に合わせた言葉で始めます。
相手の安否を気遣う言葉/h3
「いかがお過ごしでしょうか」「お元気でいらっしゃいますか」など、相手の安否を気遣う言葉が続きます。少し前にお会いした方であれば、「暑さに負けず お元気でお過ごしのことと存じます」「お変わりなくご活躍のことと存じます」などの言葉も大丈夫です。
結びのあいさつ
「暑さ厳しき折 くれぐれもご自愛ください」「残暑厳しき折 皆様のご健康をお祈り申し上げます」「まだまだ暑さは続くようです お身体を大切にお過ごしください」「お元気で暑い夏を乗り越えられるよう心より願っております」など、相手を気遣う言葉で締めくくります。
日付
「令和〇〇年盛夏」 のように年号と季節を表す言葉を入れます。
ポイントを押さえて、感謝や気遣いの心を伝えよう
お中元も暑中見舞いも、大切な方への感謝や気遣いの心をお伝えする日本の素晴らしい伝統です。
今年の夏は、しっかりとポイントを押さえて大切な方へしっかりと心をお伝えしましょう。