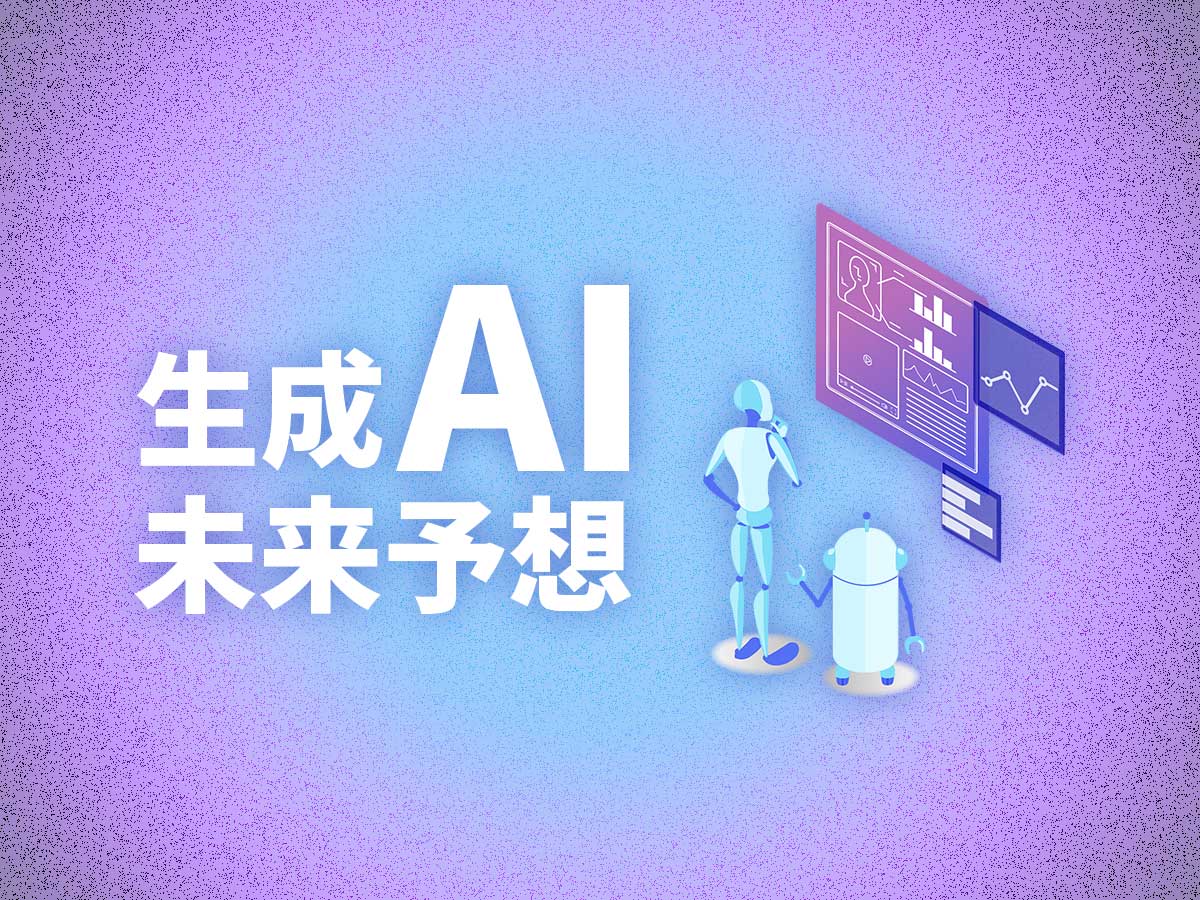
さまざまな面で進化を続けている生成AIは、もはや社会に不可欠なツールになりつつありますね。
その一方で、AI画像生成サービスをディズニーとユニバーサルが著作権侵害で提訴したというニュースも話題になりました。
この記事ではそんな生成AIの未来予想を、筆者の実体験を交えつつまとめています。

生成AIがデザインに関わる仕事を奪う?
一度でも生成AIで画像や動画を作成したことがある方なら、その速度とクオリティに驚いたことでしょう。
これまでは専門的な技術やツールが必要だった精細なクリエイティブも、描きたいイメージを指示するだけで内容もテイストも表現できてしまうのです。
デザインの現場では、人間が行う仕事は「AIが生成した大量の候補から優れたアイデアを選び出し、洗練させる役割」になると予想されています。
もしくは、非デザイナーでもAIの力を借りてこれまでにはできなかったような仕事をこなすことができるでしょう。
「AIがクリエイティブ仕事を奪う」と予想する人もいますが、実際には役割分担が進んだり非専門家が扱えるクリエイティブの範囲が広がるのではないかと考えられます。
著作権問題と生成AI
生成AIによる効率化が歓迎される一方で、特に画像や動画の生成の「効率が良すぎる」ことでの問題も発生しています。
2025年6月11日、ディズニーとユニバーサルがAI画像生成サービスMidjourneyを提供する米Midjourney社を著作権侵害で提訴しました。
これは「生成AIで作成した画像を使った商品を販売して提訴された」といったケースではなく、「AIが既存の著作物を学習しただけでも著作権侵害にあたる」と主張されたことで注目されています。
また、他のツールにあるような「特定のキャラクター画像の生成リクエストを拒否する」というような著作権侵害を防ぐ機能がMidjourneyには搭載されていないのも問題視されており、今後は生成AIを取り巻く法律や業界のルールづくりが強化されていくと考えられます。

教育現場と生成AI
生成AIの活用は、教育の現場でも着実に進んでいます。生徒一人ひとりに合わせた学習教材の提供やレポートや作文の添削、さらには教員の業務効率化など可能性は多岐にわたります。
特に注目されているのが「対話型AI(ChatGPTなど)による学びの個別化」です。従来の一斉授業では難しかった、生徒それぞれのペースや理解度に応じた指導が可能になることで学習意欲の向上や不登校・学力格差の解消につながるのではと期待されています。
一方で「子どもがAIに頼りすぎてしまうのではないか」「学ぶ力が低下するのでは」といった不安の声も根強くあります。これらは生成AIを活用する側の“姿勢”と“目的意識”に大きく左右される問題です。教育者や保護者がAIとの距離感を適切に保ちつつ、活用する道を探る必要があります。
筆者の実体験では、外国語の勉強で対話型AIが大きく役立ちました。「◯◯◯語を勉強したい」という漠然とした投げかけにも瞬時に回答があり、単語や文法の解説だけでなく「日本語との違い」や「学習する流れの提案」など、これまでに感じていたような外国語学習のハードルやストレスを生成AIによる学習ではかなり下げられると感じました。
日本での生成AIはどうなる?
総務省によると日本のAIシステム市場規模(支出額)は2023年に前年比34.5%増の6,858億7,300万円となり今後も成長を続け、2028年には2兆を超えるまで拡大すると予測されています。
世界に比べると生成AIビジネスのスピード感やスケール感は遅れをとっているのは否めませんが、国内の大手企業やベンチャーがAIシステムの開発でしのぎを削っています。
広く生成AIのビジネス利用という側面では、少子高齢化が深刻化している日本において、生成AI活用による生産性向上が期待されています。

技術革新と法整備のバランスが未来を左右する
AIがどのようなデータを学習し、どのようにコンテンツを生成するのかといった技術的な側面と、それが既存の権利にどう影響するかという法的な側面が複雑に絡み合っています。
今回のMidjourneyに対する訴訟が示すように、今後日本国内でも生成AIの急速な発展は効率化などのメリットだけでなく既存の法律や社会システムとの間で摩擦を産むことでしょう。
重要なのは、デメリットばかりに目を向けて生成AIを単なる「脅威」として捉えてしまわないことです。柔軟な視点を持って議論することが生成AIの健全な未来を築く鍵となるでしょう。
生成AIと自分がどのように関わるか
ビジネス、エンタメ、法律……もはや生成AIがまったく関係しないという分野は無い社会になりつつあります。
「難しそうな技術の話はさっぱりわからない」という方も、ぜひ自分の好き・気になる話題と生成AIの関わりについて調べてみてください。
ネガティブな話題も出てくるかもしれませんが、まず個々の人間が「当事者意識を持つ」ということが、生成AIの進化と社会のバランスをとる第一歩であると筆者は考えています。