
皆さんはAIの2026年問題というのを聞いたことはありますか?
これは、とあることによって2026年頃にAIの進化を鈍化させる可能性が問題視されています。
この記事ではAIの2026年問題をできるだけ専門用語を使わずわかりやすく解説します!
AIの2026年問題とは?
2026年問題とは、AI(特にChatGPTのようなLLMと呼ばれる大規模言語モデル)の学習に不可欠な高品質なデータ(書籍、ニュース記事、論文など)が2026年頃に不足し、AI技術の進化が停滞するのではないかという問題です。
これは既存のデータはすでにAIに学習し尽くされ、新しくインターネット上に生まれる高品質なデータはAIの学習速度や要求量に追いつかないだろうと言われているためです。
SNSなどノイズの多いデータはAIの学習には不向きであり、また個人情報保護などAI学習に関する規制が強化され高品質なデータ不足がさらに加速するであろうことが心配されています。
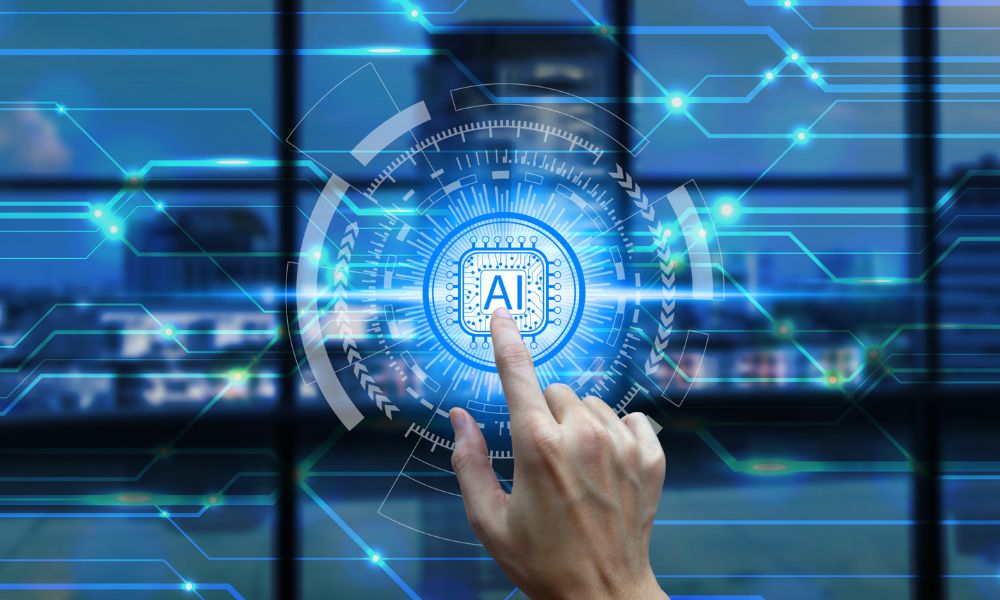
2026年からAIの進化が止まってしまう?
現在は日々進化の目まぐるしいAI技術ですが、この発展は学習データの質と量に大きく依存します。
また、学習データ不足は、現在利用されているAIの改善だけでなく精度維持にも悪影響があります。
AIが劣化する「モデル崩壊」とは
AIが自ら生成したデータを再び学習に使うことで、出力品質が徐々に低下していく現象をAIの「モデル崩壊」と言います。
これは高品質な学習データが不足している時に強く現れ、2026年問題で心配されている懸念のひとつです。
AIの2026年問題がもたらす生活への影響
このまま学習データ不足の状態が続けば、ビジネスや医療・金融などAIが活用されているさまざまな分野で悪影響を及ぼすでしょう。
また、日本語の高品質なデータは英語に比べて量が少ないため、AI2026年問題はより顕著になる可能性があります。
求めている情報になかなか辿り着けなくなったり、動画サイトやECサイトのおすすめ機能の精度が下がったりという身近な生活にも問題が起こるかもしれません。
AIの2026年問題への対策
AIの2026年問題が初めて指摘されたのは2022年11月にAIの研究機関である「Epoch AI」によるもので、2023年にカリフォルニア大学のスチュアート・ラッセル教授が国際的なイベントのインタビュー内で言及されたことで広く知られるようになりました。
より効率よくデータが学習できるようなモデルの開発や画像や動画、行動データなどテキスト以外のデータからも学習ができるようにする手法など、今日に至るまでさまざまな対策が進められています。
そもそも大規模な学習ありきのモデルではなく、医療など特定の分野では専門的なデータに絞り学習して精度を高める「小規模言語モデル」の活用も進められています。

2026年問題は2028年問題へ?
Epoch AIは最新の研究結果等を踏まえた2024年の論文で、改めてAIが学習するデータの枯渇が2028年頃になると述べています。
上記で述べたような2026年問題への対策が実を結びつつあるとも言えますが、問題が後ろ倒しになりつつも抜本的には解決していないことがわかります。
AIの2026年問題を対策する技術の発展が先か、本当にAIが学習し尽くしてしまうのが先か、今後の動向に注目が集まります。
AIのデータ学習と日本の法規制
日本では2025年5月28日に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(通称:AI推進法)」が成立し、同年6月4日に一部施行されました。
この法律では国がAIの悪用リスクに対応して国民の不安を和らげつつも日本でのAI活用を促進することを目的としています。
一方で”個人が特定できない形でのAI学習に限り”個人情報の利用に本人同意を不要とする例外を設ける個人情報保護法の改正案も検討されており、AIのデータ学習をめぐる日本国内の動きも2026年問題を前に転換期を迎えるかもしれません。

まとめ
「このまま進化し続けていったらどうなってしまうんだろう…」と思ってしまうほど劇的な進化を続けてきたAI技術ですが、その急激な進化ゆえに”学習データが底をついてしまう”という心配が「AIの2026年問題」でした。
AIの学習データの確保は技術的な問題だけでなく、権利や倫理的な問題も絡んで今後より複雑になっていくことでしょう。
これからの数年間は、おそらく大きな転換期となることでしょう。ぜひ今後のニュースにも注目してみてください!