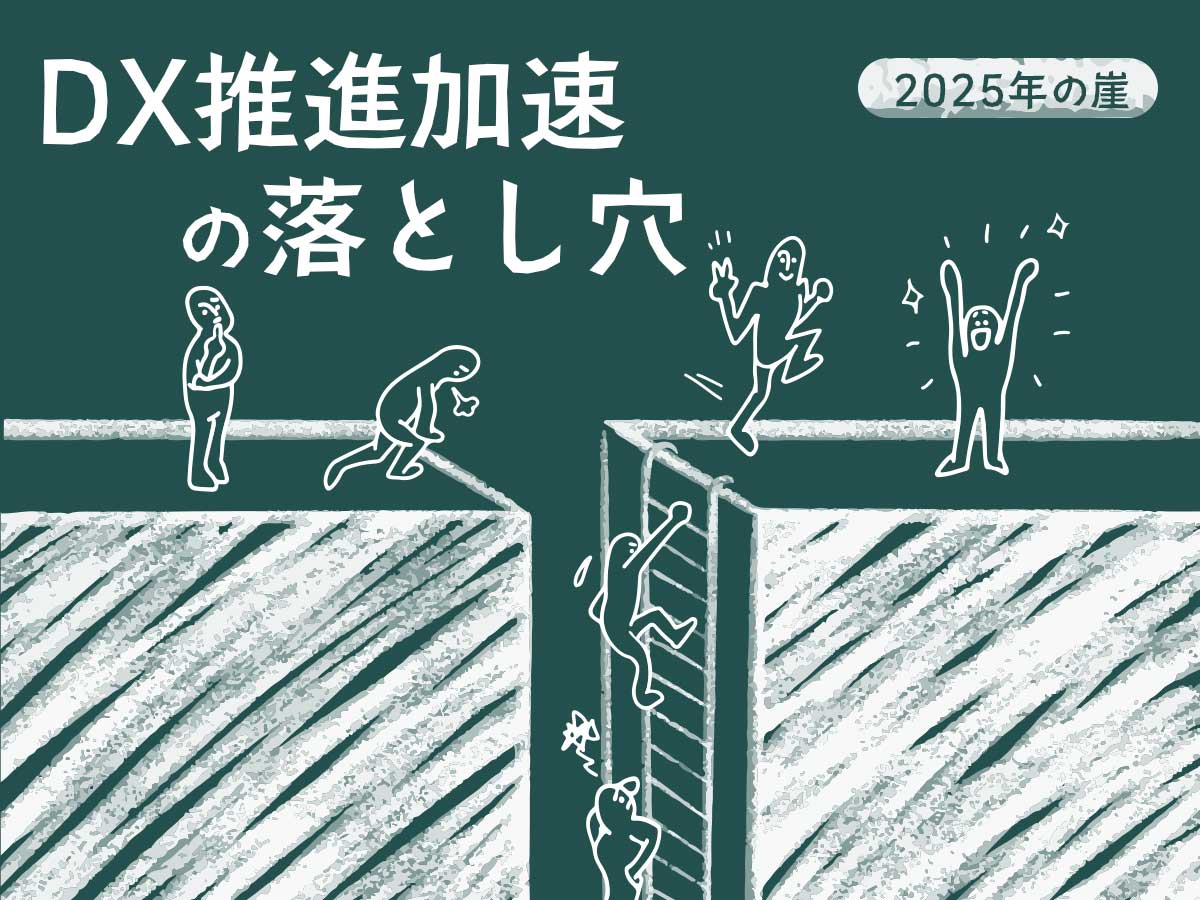
2018年に経済産業省のレポートで提唱された「2025年の崖」をご存知ですか?
現在も思ったような成果が出ずにDX推進を加速しようと思っている企業も多いかもしれません。しかし、ただ成果を急ぐだけでは逆効果になるケースも多いんです。
本記事では、DX推進を阻害する要因や”あえて”DX推進を減速すべき理由を解説します。
2025年の崖とは?
経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」では、日本企業が直面する重大な課題として「2025年の崖」が警告されています。
これは2025年以降に老朽化・複雑化したレガシーシステムの維持に膨大なコストとリスクが発生し、さらにIT人材不足や技術者の高齢化により刷新が困難になることで、年間最大12兆円規模の経済損失が生じる可能性があるというものです。
背景には導入から20年以上経過したシステムの延命利用、異なる部署ごとのバラバラなシステム構築、そして経営層のDXへの意思決定の遅れがあります。これらの課題を放置すれば、競争力の低下だけでなく、セキュリティ事故や事業継続の危機を招く恐れがあります。
「2025年の崖」をいかに乗り越えるかは避けて通れないテーマですが、DX推進に課題を抱えている企業が現在においても多くあります。

DX推進を阻害する5つの要素
トップの熱意と現場の温度差
経営層がDXを積極的に発信することは重要ですが、実態が伴わないまま複数のプロジェクトを乱立させると現場の混乱を招きます。目的や優先順位が曖昧なまま進めることで形だけのDXとなり、現場の信頼を失ってしまうのです。
最新テクノロジー依存
AIやクラウドなどの最新技術はDXの大きな推進力ですが、「導入ありき」の姿勢は危険です。テクノロジーはあくまで課題解決のための手段。目的と手段が逆転すると、DX推進加速どころか余計なシステム負担や運用コスト増加を招きます。
スピード重視の人材配置ミス
DXプロジェクトはスピード感が求められますが、経験やスキルが不十分な人材を重要ポジションに配置すると判断ミスが発生しやすくなります。結果的にやり直しや遅延が発生し、当初の加速計画が崩れる危険があります。
縦割り文化の加速
部署ごとに個別でDXを進めると、統合不可能なシステムやデータが乱立します。本来、DXは組織全体の最適化を目指すものですが、逆に部門間の溝を深める結果になりかねません。
“変化疲れ”による離職
急激な業務変革は現場の負担を増やし、精神的・肉体的な疲弊を招きます。新システム対応や追加業務で日常業務が圧迫されることで、優秀な人材が離職するリスクも高まります。
あの有名企業も!? DX推進の失敗例
部門分離が招いたDX推進の失敗
米自動車大手フォードは、デジタル分野でのDX推進を目的に、シリコンバレーに子会社「Ford Smart Mobility」を設立。しかし、本社の製造部門と切り離して運営した結果、部門間の連携が不十分となり、最終的に数億ドル規模の損失を計上しました。
DXは全社一体の体制で推進する必要性を示す象徴的な事例となりました。
技術先行で失敗した観光DX
ある旅行会社は、コロナ禍で実際の観光が制限される中、新たな収益源としてバーチャル観光サービスを急遽立ち上げました。最先端の映像技術やオンライン配信環境を整備し、遠隔地からでも観光地を楽しめる体験を提供しようと試みましたが、開発段階で顧客ニーズの調査や市場分析が不十分だったため、利用者数は伸び悩みました。
この事例では、DX推進において技術導入よりも先に、顧客視点での価値創造を深く掘り下げる必要性を示しています。
DX推進をあえて“減速”すべき理由
小さく試して大きく育てる
DXは一度で完成させるものではなく、試行錯誤を繰り返しながら進化させるプロセスです。小規模な概念実証(PoC)から始め、成果と課題を確認しながら拡大していく方が、結果的に加速につながります。
現場文化の醸成に時間が必要
ツールやシステムの導入だけではDXは成功しません。現場の理解と協力を得るためには、時間をかけた説明や教育、段階的な導入が不可欠です。
「止まる勇気」が失敗を減らす
計画を一時停止し、方向性や目標を見直すことは後退ではありません。むしろ不要な投資や失敗を未然に防ぎ、長期的な成果を確保するための重要な判断です。
成功のための“アクセルとブレーキ”戦略
明確なKPIとマイルストーン設定
DXロードマップにおいては、全体的なビジョンに加えて、3カ月以内に特定施策を完了するといった明確なマイルストーンを設定し、進捗管理を行うことが鍵となります。例えば、「業務プロセスを◯%効率化」「特定業務を◯日短縮」などの定量的なKPIが重要です。
定期的なプロジェクトレビュー
計画に対して定期的にレビューを行うことで、課題やリスクを早期に把握できます。多くのフレームワークでも、KPIとマイルストーンを軸にしたPDCAサイクルを取り入れることが推奨されています。
外部パートナーとの協業
外部のコンサルタントやベンダーは、多業種におけるDX支援の豊富な経験を持っており、自社では見えづらい課題や解決策を提案できる貴重な存在となります。

ある中小製造業では、大学やスタートアップなど外部パートナーを巻き込んだオープンイノベーション型のDXを実践し、短期間で生産効率や品質向上を実現しています。
外部との柔軟な連携は、内部だけでは得られない視点と技術導入を可能に。 従来の“受け身のアウトソース”から脱却し、パートナーが戦略的な立場で一体となる「共創型」の関係構築がDX成功につながります。
単なる開発スキル提供だけでなく、業務課題の本質や経営視点を共有できるパートナー選びが重要です。
DX推進加速は目的ではなく手段
DX推進加速は企業の成長を支える重要な要素ですが、それ自体がゴールではありません。
真の目的は、持続的な競争力と顧客価値の向上。目的を見失わずに意思決定することが大切です。
加速すべきタイミングと減速すべきタイミングを見極め、戦略的にアクセルとブレーキを使い分けることがDX成功への最短ルートとなります。
